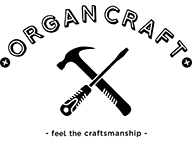街に貼られたポスター、数々の雑誌のファッションページ、コレクションのランウェイ。どこかあどけなさの残る顔つきに、覚めたような目つきが不釣り合いで印象に残る。「モデル目指してたわけじゃないんです。それは今でも変わらない」と、Keigoは言う。東京に来たのは18歳の頃。地元の高校を出て、都内の印刷会社に就職した。

「エミネムに憧れたんですよね。工場で働きながらヒップホップやるっていう、映画の『8 Mile』がそんな感じで。当時は家帰ってビート作って、オールで遊んでまた工場出かけるみたいな、そんな生活で。今思うとピュアですよね。その頃仲良くなった人伝いで、ヴェトモンっていうブランドのショーに出てみないかって誘われたんです。しばらくパリに行くから、仕事辞めなくちゃいけなくて。好きだったんですけどね、工場の仕事」
パリから帰ってきたらモデルとして見られるようになっていた。それから、撮影のオファーが続いた。でも、当時のKeigoは、ファッションとは縁遠い生活。世界で最も影響力があると言われるそのブランドのことも知らなかった。
「撮られること自体より、アウトプットが形になるのが楽しいっていうか。だからモデルとして目立ちたいとかじゃないんです。昔から、自分が前に出るより、誰も見てないところで一人でやってるのが好きだから。感覚的には、今たまたまモデルっていう武器で仕事させてもらってて、その次のために音楽を蓄えている感じです」
Keigoは正直な言葉で、素直に話そうとする。でも、話の流れでちょっといい言葉がこぼれると、恥ずかしそうに照れ笑いでごまかす。まるで、カッコつけることが、カッコ悪いみたいに。

「自分がダサさに気づける瞬間が、けっこう気持ちいいんですよね。またひとつ手に入れたっていうか。前にすごい恥ずかしいことやっちゃって。仕事辞めたばっかりで音楽に気合い入ってて、初めて自分でイベント組んだんです。手当たり次第に人を呼んで、小さな飲食店にめちゃくちゃ人集まって。でも、僕が当時作ってたビートって若造が勢いで作っただけみたいな、今思うとすごい恥ずかしいもので。自分がいかにできてないかすら、わかってなかった。ダサかったですよ。実力が伴ってないのに、変な自信と勢いだけあって。でも、そこから大人になったと思います。今はビートメイクもエンジニアリングも勉強してて。ちゃんと音楽を学んで成長したいって思うから」
仕事がない日は、ほとんど一日中部屋にこもって音楽を作る。一番長く時間を過ごす場所だから、デスクにはこだわりたかった。オーダーメイドで作ったのは、機材と部屋の配置から考えられた、装飾を排除したシンプルなデザイン。それは、まっさらな状態で自分自身の感覚に向きあうため。窓の光を受けて表情を変えるアクリルは、部屋の中でも時間の移ろいを感じさせてくれる。

ファッションやモデルの仕事、音楽との向き合い方。東京に出てきてからの3年で、Keigoは大きく変わった。何もかもが輝いて見える無邪気な若さと引き換えに、自分にとって大切なものを見据える目を養ってきた。
「毎晩飲んで騒ぐよりも、楽しいこと見つけちゃったんです。家で音楽作ってる時間が、やっぱり好きだから。今、自分にとって一番大切なのって、彼女との生活。そのためにモデルと音楽っていう武器を磨いていきたいんです。夢ってわけじゃないけど、彼女にもっといい暮らしさせられるようになって、彼女の親に認めてもらえる人間になりたいです。グレてたり遊んでるより、その方がカッコいいって思えるようになったんで」
Text:Masaya Yamawaka(1.3h/イッテンサンジカン)
Photo:Fumihiko Ikemoto(PYRITE FILM)