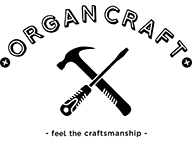誰かの記憶に刻む「あの時の料理」を作る
潮風が吹き抜ける歴史残る街、鎌倉は七里ヶ浜にある創作フレンチ・イタリアン「DRAQUIRE(ドラキア)」。その店のオーナーシェフは、幼少期はイタリアに暮らし、数々の有名なレストランで働いた経験を持つ山田尚立(やまだ しょうりゅう)さん。今回は、そんな山田さんのクラフトマンシップに迫る。

海外を渡り歩いて導き出した料理の道
2歳から10歳くらいまでイタリアに住んでいたという山田さん。幼少期のイタリアでの記憶を傍に置きながら、どんな道を辿ってこの料理の世界へと入ったのだろうか。
「高校卒業とともに上京して2年間位フリーターをした後、元々海外に行きたかったしイタリアにも戻りたかったので、現地の大学に入ろうと語学留学と受験の準備のためにイタリアに1年間滞在しました」
20歳で再度イタリアへと渡り、ヨーロッパ各地を気ままに旅していたという。その頃料理は「興味はありましたが、やりたいとは全く思っていなかったです。むしろ何にもやりたくなかったです(笑)」と山田さん。でも、食べることは元々好きで、各地で食を楽しんでいたとか。
それからイタリアで進学はせず、帰国して日本の大学に入ることに。金融を専攻して、在学中にインターンで働くも空気感が合わなかった。その頃、知り合いがやっていたワインバーでたまたま働くことになり「じゃあ、料理やるか」と、ここでスイッチが入ったそう。この時27歳。山田さんが本格的に料理を始めることになった。

誰かへ伝える。自分の記憶に残る「味」
それから南青山のイタリアンレストラン「イル・テアトリーノ・ダ・サローネ」で修行を始める。店では皿洗いなど基礎的な雑用をこなし、自分で食材を買い家で真似をして作る日々。現在は閉業したホテル「クラスカ」では、レストランでスー・シェフを務め、ウェディングでは何百人前もの料理を仕上げる現場能力を身につけた。その他色々な店を経験しながら、白金高輪のフレンチレストラン「オレキス」で5代目ヘッド・シェフとなる。
「スー・シェフの時もメニューを考えたことはありましたが、フルコースで毎月自分の考えたメニューで回していくのはオレキスが初めての経験でした。店の移転による一時閉店が決まってからは、『最後にあの時のあれが食べたい』と言って下さるお客様もいて、自分の料理にも覚えて頂けるものがあるのだなと嬉しかったですね」

味覚は人の差が大きく出るもの。そして人は、毎日の「食べる」という行為によって、文字通りに数えきれない味を感じていて、メモリ容量の限界がある記憶の中では、一定量を超えると上書きされていく。それでも記憶の棚に新たな引き出しを作るような、忘れられない「あの味」とは、どんな味なのだろうか。山田さんはどのようにして覚えてもらえる料理を作っているのだろう。
「あまり言語化出来ませんが、同じように自分の記憶に残っている“何か”を作っているのだと思います。例えばイタリアに居た時にすごく美味しかったご飯とか。料理じゃなくても、例えば写真なら、こういう風に撮るとキマるというパターンみたいなものがあると思いますが、それって多分自分では意識していないですよね。そういうものが無意識に自分の中にデータのように蓄積されていて、そこから引っ張り出して作っているのかなと。幼少期にイタリアに居たことは、今の自分にとっても凄く大きなことだったと感じています」
イタリアンで基礎を学び、フレンチでも修行を重ね、フレンチにはないパスタとイタリアンにはないソースなど国々の特色を修得した山田さん。そしてオープンさせたDRAQUIREでは、ジャンルに囚われずに素材同士が自由に互いの味を引き出す一品を提供している。後編では、気になるメニュー作りについて深掘りしていく。
INTERVIEW&TEXT: Natsumi Chiba
PHOTO:Shu Kojima
山田尚立
1985年生まれ。幼少期から青年期の多くをヨーロッパ各国で過ごし、料理の道を志してからはイタリアンのイル・テアトリーノ・ダ・サローネ、フレンチのミシェル・トロワグロ、北欧のノーマの遺伝子を継ぐイヌアなどを経て、白金高輪オレキスのヘッド・シェフを務めたのち独立。縁の深い鎌倉にDRAQUIREをオープン。
Instagram: https://www.instagram.com/_draquire_/ (@_draquire_)